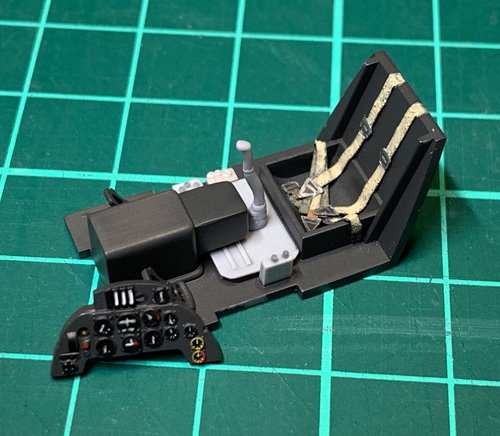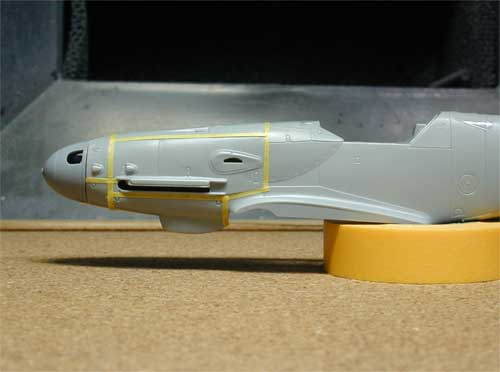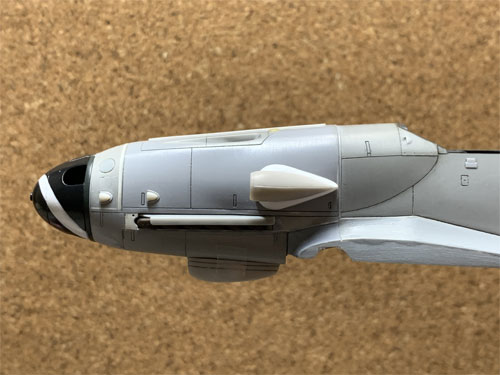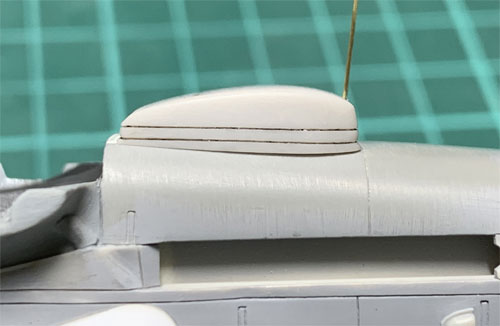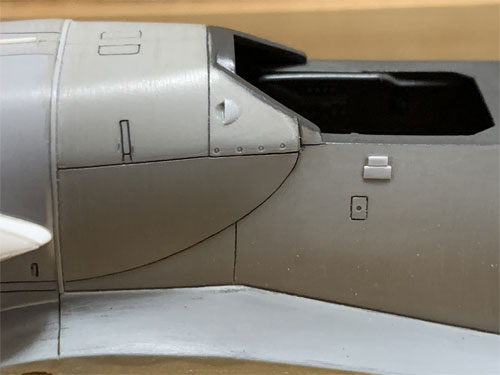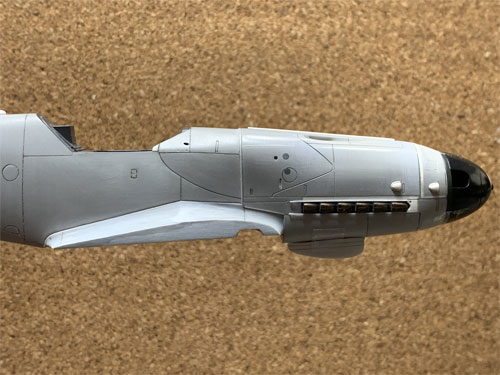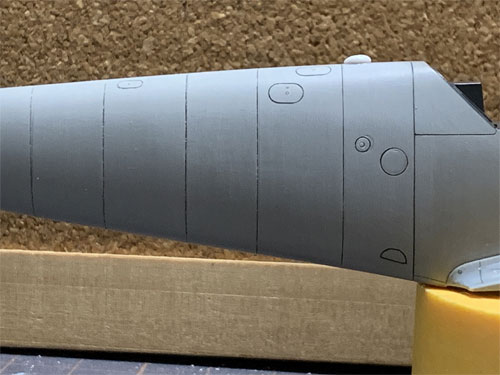●再開
当初、ハセガワG−10で進めていたが、途中で気が変わりレベルベースに変更。
マーキングは2./JG300、W.Nr.不明、 Rita赤2番機、Eberhard Gzik機。
この機体も不明な点が多く型式も諸説あり、490000番台ならErla製G−10ではあるが、460000番台 (Erla製 G−14からの改造)との読み間違いなのでは?などなど・・・・。
今回も数枚の実機写真を元に楽しみたいと思う。
尚、当サイトではErla製G−14/ASとして進めていく。
(2007〜) |
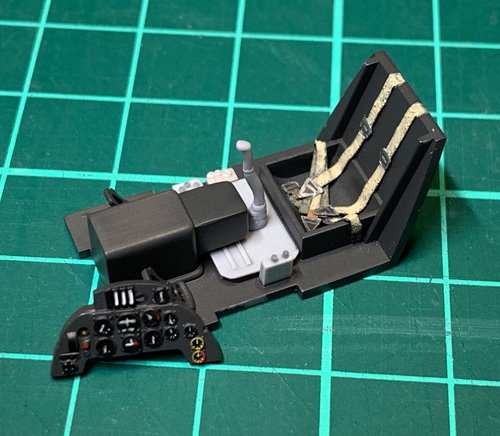 |
2020/6/4
先ずはコクピットから。
正面計器板、フットペダルはフジミ、コクピットフロアはハセガワ、操縦桿はエアから流用、プライマーポンプはプラ板、伸ばしランナーで再現。
底板は後期の簡易タイプに変更。
シートベルトはコーヒーフィルター、バックルはコピー紙、接着はアラビックヤマトのり。 |
 |
燃料パイプは伸ばしランナー。
FuG25a無線機操作盤とパイロット・ヘッドフォン音量調節装置のレアウトは、キットのスペースの都合上G−6と同じにした。 |
 |
24Vバッテリーカバーはエデュアルドから流用。 |
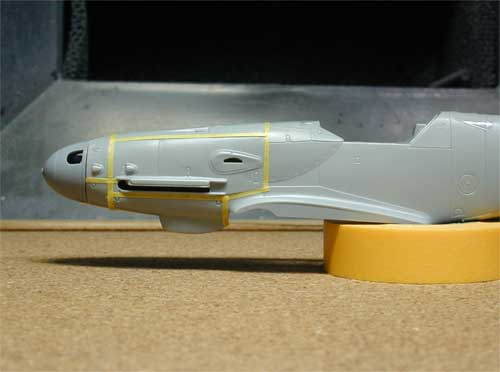 |
キットの機首は2mm長い(防火壁〜風防手前)ので切り詰め、側面形は上下ラインを修正。
オデコとエラを張らせる。
マスキングテープが切断位置。 |
 |
修正前(後)と修正後(前)の比較。
機首は防火壁〜風防前部で2mm詰める。
あと、排気管の位置を少し下げる。 |
 |
左舷カウルの頂点はインペラ中心部、主脚に繋がるエンジン架を意識して削る |
 |
機首潤滑油タンクを大型化したのに伴い、給油ハッチもやや上に移動。 |
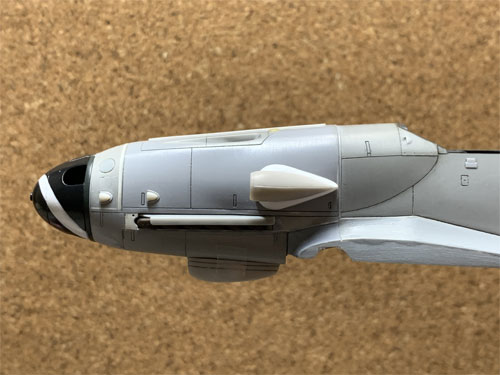 |
排気管カバーは左舷側上部はハセガワ、その他は0.2透明プラ板。
主脚側に逃げるエンジン支持架を伸ばしランナーで追加。 |
 |
継ぎ足しカウルはゴムシーリングに向かってのラインも左右非対称。
|
 |
キットの排気管上部ラインはなだらかな曲面だが、実機はG-6をベースにしているので直線になる様に削り込んだ。 |
 |
オイルクーラーの変更(FO870→FO987)に伴い、オイルクーラーカバーも大型化した。 |
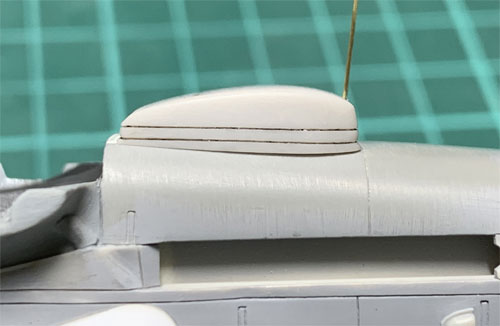 |
再生機なので従来のカウルを継ぎ足して使用。カウル前部先端は段違いのまま(D-9の延長プラグと似た処理)、後端は影で不明なので推定で先端部と同じ処理にした。 |
 |
オイルクーラーカバーはフジミを流用。
フジミはサイドが膨らみ過ぎなので、軽く削った程度で妥協。
攻めるなら後、0.5mm狭めると良い。 |
 |
4分の1半月パネルはキットのモールドの様なリベットは確認出来ず、木口に沿って細かくリベットが打たれているので省略。 |
 |
左舷側の膨らみは、カウル中央部のパネルライン直後から始まる。
G-6ベースなので継ぎ足しカウル以外はスッキリとしたラインになる。
インテーク基部はやや誇張しているが、取り合いのラインでこの部分曲面が判る。
最大値はインペラ中心部。 |
 |
排気管は排気ロスを軽減する為、やや下向きになっている。
インテークは若干上向きになっている様だ。 |
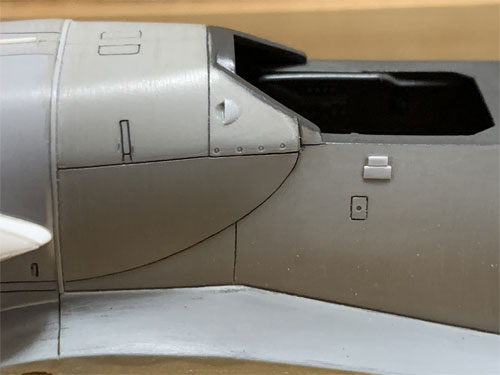 |
風防側面下のエアスクープは溝を彫り込んだ。天板側も少し押し広げた様に見えるのでプラ板で再現。
メーカープレートは2枚。 |
 |
手掛け下に用途不明の○パネルがあるので追加。
しかもこの○パネルは機体毎に微妙に位置が違うのが悩ましい。
推測であるが、製造時にのみMW50装置の調整に必要なハッチかも? |
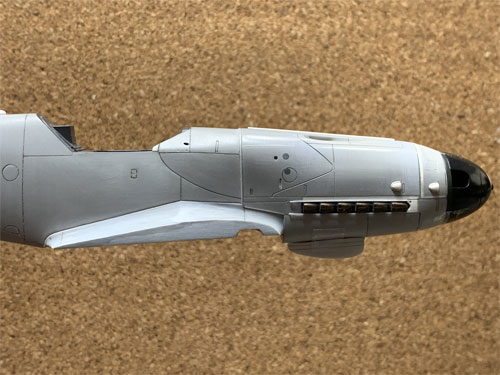 |
コクピット換気用ハッチは左右で位置が違う。恐らく右舷側のサーキットブレーカーを避けて、やや後に開口したのだと思う。
因みにタミヤグスタフは抜かりなく再現している。>流石 |
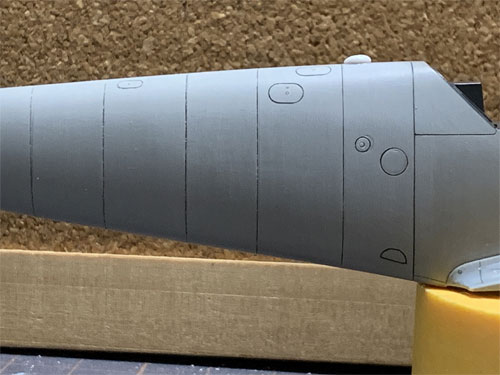 |
MW50装備なのでハッチも追加。 |